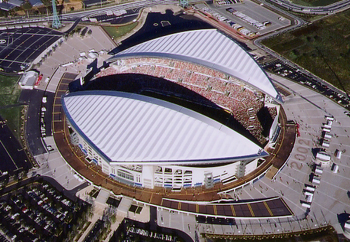|
Q&A
|
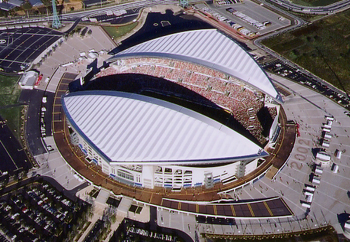
(c)埼玉新聞社提供 |
| Q1 登記される権利にはどんなものがあるのでしょうか? |
| A: |
土地と建物についての所有権、地上権、永小作権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権の9つの権利について登記することができます。(不動産登記法第1条) |
|
| Q2 登記にはどんな種類があるのでしょうか? |
| A: |
いろいろな分類方法がありますが、以下に代表的なものを回答します。
| 1) |
「表示の登記」と「権利の登記」との分類
「表示の登記」とは物理的現況を公示する登記です。例えば「建物を新築」したり、「土地の地目」に変更が生じた場合です。この業務に関しては専ら土地家屋調査士が代理業務を担います。
「権利の登記」とは、Q1で回答した権利関係を公示する登記です。例えば、土地を購入したり、お金を借りて抵当権を設定したという場合です。この業務に関しては専ら司法書士が代理業務を担います。 |
| 2) |
登記の記載内容による分類
「記入の登記」とは、売買など新たに発生した原因により、初めて登記簿に記入する登記です。
「変更の登記」とは、既に登記された事項の一部を変更する登記です。(例えば、所有者が住所異動があって変更が生じた場合です。)
「抹消の登記」とは、登記された事項の全部を消滅させる登記です。(例えば、債務弁済により抵当権を抹消させる場合です。)
「回復の登記」とは、登記された事項が不当に消滅された場合、その登記事項を回復させる登記です。 |
|
|
| Q3 嘱託登記とは? |
| A: |
これも登記の種類として「申請による登記」「嘱託による登記」「職権による登記」に分類されるうちの一つです。
「申請による登記」とは、私人当事者による登記手続をいい、「嘱託による登記」とは、官公署が当事者として為す登記をいいます。
「職権による登記」とは、登記官が申請あるいは嘱託なしで為す登記です。
|
|
| Q4 |
昭和初期に登記された抵当権が抹消されないまま現在に至っています。この登記を抹消する方法は? |
|
| A: |
まず、そのような抵当権を「休眠抵当権」と呼びます。
手続としていろいろな方法がありますが、(1)債権者(登記義務者)が行方不明であること(2)債権の弁済期から20年を経過していること(3)債権、利息、損害金の全額を供託すること等の要件を充たすことで、不動産所有者より抹消登記ができます。個々のケースにより手続が異なりますので具体的にご相談下さい。
|
|
| Q5 |
用地の取得にあたり名義人が死亡しています。ついては、相続について教えて下さい。 |
|
| A: |
亡くなった人(被相続人)の死亡時期(相続開始年月日)により相続の態様が異なります。(1)死亡時期が昭和23年以降の場合「新法による相続(現行法)」となります。(2)死亡時期が昭和23年前の場合「旧民法による相続(家督相続、遺産相続等)」となります。どちらにしても、戸籍等を取り寄せる(相続人を特定する)作業が必要となり、相続の態様に応じて相続人らに充分ご理解いただいたうえ、権利の取得者を確定していただく事となります。 |
|
| Q6 |
用地を取得するにあたり所有者(名義人)が痴呆ぎみなのですが、どのような点に注意したらよいでしょう。 |
|
| A: |
判断能力に疑問のある者との法律行為は、後で取消される恐れがあります。
平成11年に民法が改正され成年後見制度がスタートしました。この制度を利用することにより安全な取引が可能となります。
(成年者の判断能力に応じ家庭裁判所に以下の申立をする。)
1)判断能力不十分→補助開始の申立
補助人(同意権)を選任
※特定の法律行為につき代理権を付与する申立も可。
2)判断能力著しく不十分→保佐開始の申立
保佐人(同意権)を選任
※特定の法律行為につき代理権を付与する申立も可。
3)判断能力を欠く常況→後見開始の申立
後見人(同意権)を選任
※包括的な代理権
|
|
|
|